本文
令和7年度「肝臓週間」について
肝臓週間について(令和7年7月28日~8月3日)
世界保健機関(WHO)は、平成22年から毎年7月28日を「世界肝炎デー」と定め、ウイルス性肝炎のまん延防止及び患者・感染者への差別・偏見の解消、感染予防の推進を図ることを目的として啓発活動を実施しています。日本も、平成24年に7月28日を「日本肝炎デー」と制定し、世界肝炎連盟が展開する世界肝炎デーの活動に参加するとともに、公益財団法人ウイルス肝炎研究財団主催の「肝臓週間(7月28日を含む週の月曜日から日曜日まで)」に集中的な啓発活動を行っています。
これに呼応して、県においても、次のとおり肝臓週間啓発活動等を行います。
プレスリリース(令和7年7月18日公開) [PDFファイル/147KB]
県庁本館ドームのライトアップ
実施期間:令和7年7月25日(金曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで
実施時間:日没(19時30分頃)~21時00分
内容:日本肝炎デーのシンボルカラーである「スカイブルー」で県庁本館ドームをライトアップします。
県庁のほか、拠点病院である愛媛大学医学部附属病院等でもライトアップを実施予定です。

街頭啓発活動
実施日時:令和7年7月26日(土曜日)14時00分~16時00分
実施場所:銀天街出入口周辺(松山市湊町5丁目1-1)
内容:愛媛大学医学部附属病院の肝疾患診療相談センターと協力して、肝炎・肝がん撲滅を目指して、チラシ等を配布します。
肝炎の基礎知識
ウイルス性肝炎とは
ヒトの肝細胞内で増殖し、肝炎を引き起こす原因となるウイルスを「肝炎ウイルス」と呼びます。
肝炎ウイルスには、血液を介して感染するB型、C型と、経口感染するA型、E型等があります。
このうち、B型、C型は慢性化することがあり、放置すると慢性肝炎から肝硬変、肝がんへと進行する場合もあるので注意が必要です。
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、悪くなっても症状がほとんどなく、気付かないうちに重症化してしまうので、早期発見が重要です。
「肝がん」の原因の約半数はB型・C型肝炎ウイルスによるものと言われており、ウイルスに感染しているかどうかは、「血液検査(HBs抗原・HCV抗体等)」で分かります。
市町で行う特定検診や職場の健診(追加オプションであることが多いです)、妊婦健診等で既に検査を行っている場合があるので、ウイルスに感染していないか、一度結果をチェックしてみましょう。
肝炎ウイルス検査を受けたことがない(受けたかどうかも分からない場合も含む)方を対象に、無料検査を実施しています。
検査は、行きやすい場所や時間に合わせて、各保健所や県内約400か所以上の委託医療機関から選んで受けることができます。
自分がウイルスに感染していないかどうか、この機会に確認してみませんか?
詳しくはこちらをクリック↓
感染経路について
B型・C型肝炎ウイルスは、感染している人の血液が感染源となって他人に感染します。
近年の日本では、感染に関する知識が普及し、日常生活の場での新たな感染はほとんど見られなくなっていますが、以下のような場合には注意が必要です。
○不特定の人と注射器・注射針等を共用した場合
○不特定の人の血液が付着している針などを誤って刺した場合
○出血を伴う刺青、ピアス装着時の穴開けなどの際に、血液が付着している器具を繰り返し使用した場合 等
※B型肝炎:昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種(注射器連続使用)を受けたことがある方
※C型肝炎:過去(おおむね平成6年以前)に出産や手術で大量に出血し、血液製剤等の投与を受けたことがある方
肝臓の基礎知識
肝臓の位置・特徴
肝臓は体の中央右寄りにある臓器で、約1.2~1.5kgあり体の中で最も重い臓器です。
生きていくために必要な機能を多く担っています。
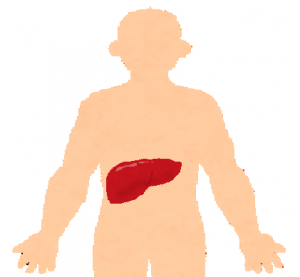
肝臓の機能
(1)代謝
胃や腸で分解・吸収された栄養素(糖・脂質・タンパク質など)をエネルギーに変換し、余ったものを貯蔵します。
(2)胆汁生成
脂肪の消化吸収に重要な「胆汁」を作り出します。
(3)解毒
人体にとって有害な毒素(アルコール・アンモニア・薬物など)を分解し、体の外へ排出します。
(4)免疫
腸管から入ってきた有害物(細菌・ウイルス等)から体を守ります。
その他(関連リンク)
肝炎ウイルス検査を受けましょう(松山市)<外部リンク>
愛媛大学医学部附属病院肝疾患診療相談センター<外部リンク>
厚生労働省肝炎対策推進室<外部リンク>
肝炎情報センター<外部リンク>
日本肝臓学会<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課 感染症対策グループ
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2402 Fax:089-912-2399
メールでのお問い合わせはこちら










